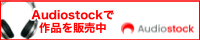川崎 絵都夫
Etsuo Kawasaki
1959年東京生まれ。魚座。A型。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。作曲を松村禎三、石桁真礼生、永富正之、國越健司の各氏に師事。
坂本龍一のオーケストレーターを勤めて以降、東京交響楽団、東京都交響楽団メンバーズアンサンブル等の編曲多数。
文化座・文学座などの新劇、劇団たんぽぽ・ACO沖縄などの児童演劇、明治座・新歌舞伎座などの大劇場公演等、舞台音楽も多数手掛ける。
その他にも邦楽器のための作品、室内楽、声楽曲、合唱曲、オーケストラ作編曲、コンピューターによる音楽制作等、幅広く活動。
現在、日本音楽集団団員。
受賞その他
ミュージカル〈ポン太〉が国の児童文化財に指定される。TVドキュメンタリー「ロシアにアメリカを 建てた男」(音楽を担当)が第14回世界テレビ映像祭・地球の時代賞コンクール審査員特別賞受賞。
音源は以下で視聴できます。

舞台
ミュージカル〈ポン太〉
かやの木芸術舞踊学院(1998年度 国の児童文化財指定)
リア王
新国立劇場
吉原炎上
新橋演舞場
氷川きよし特別公演(第一部・演劇)
明治座・新歌舞伎座
くにこ
文学座
CD
川崎絵都夫 邦楽作品集「花織」「神の風音」 「蒼き狼の夢」
「竹桐之賦」
川崎絵都夫 児童合唱作品集
(ユニバーサルミュージック ジュニアコーラス21/第14巻)
子供のためのピアノコンチェルト「不思議の国の冒険」
(東京IMC)
樹木頌〜二十絃箏とチェロ・二重奏の新しい世界〜
(石川憲弘・只野晋作プロデュース)
Playing the Orchestra
〈坂本龍一+東京交響楽団ライブ〉(編曲)
出版
とおの のはらうた/夕暮れの情景
(いずれもカワイ出版)
対話式! 「なぜ?」が分かるとおもしろい和声学〈基礎編〉
(フェアリー)
促成聴音
(全音楽譜出版社)
音大受験講座! わかりやすい楽典の教科書
(フェアリー)
蒼月譜/秋麗之賦/春うらら/秋の舞
(家庭音楽会出版部)
邦楽
花織(邦楽アンサンブル)
蒼き狼の夢(邦楽アンサンブル)
せせらぎの詩
隅田川(邦楽オペラ)
その他
映画「ラスト・エンペラー」編曲
スーパー歌舞伎(市川猿之助)用 邦楽大合奏アレンジ及び作曲
他に放送、映画、ビデオ、CM,編曲多数

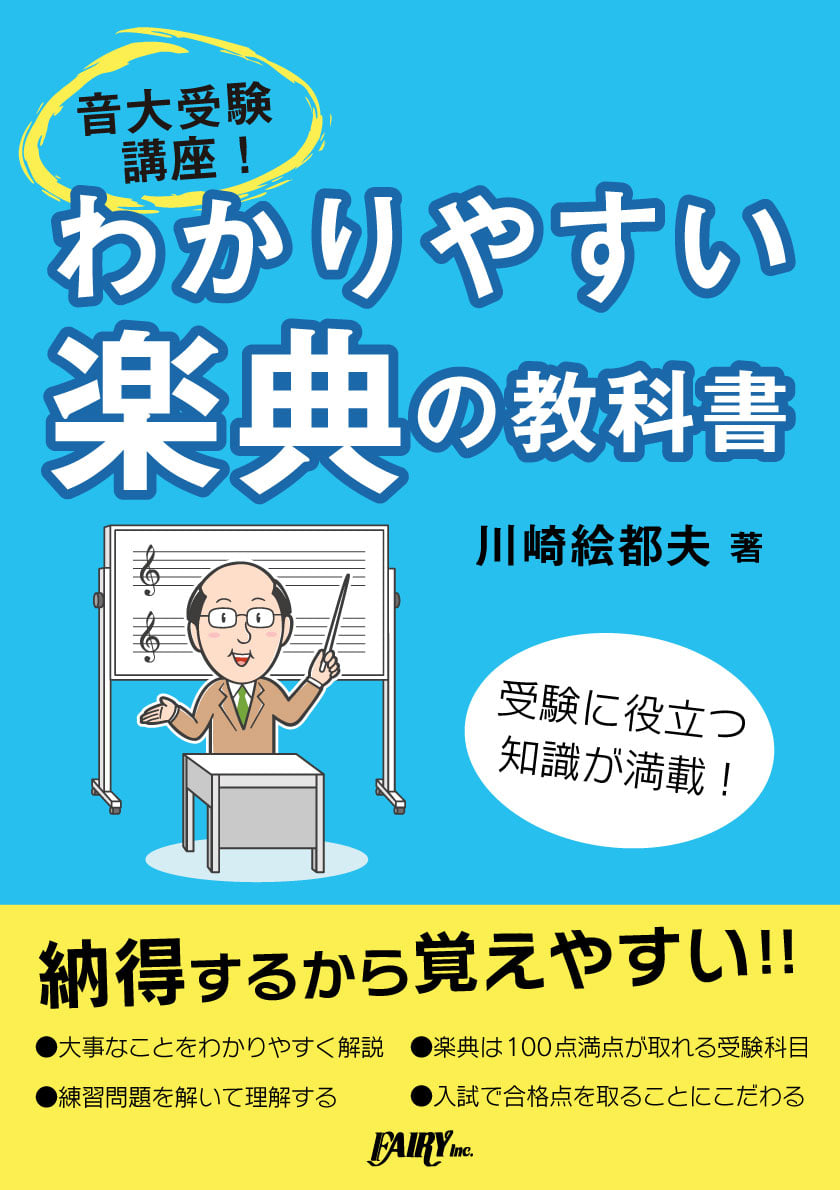
出版社:株式会社フェアリー
音大受験講座! わかりやすい楽典の教科書
川崎絵都夫 著
1,944円
●音大受験に役立つ知識が満載
●大事なところをわかりやすく解説
●練習問題を解いて理解する
●入試で合格点を取ることにこだわる
●楽典は100点満点が取れる受験科目
「楽典を効率よく勉強する方法はありませんか」?という声を音大受験生などから聞くことがあります。この教材は、そんな声に応えるために「大事なところをわかりやすく説明する」、そして「楽典で点数を稼ぎ、入試で合格点を取れるようにする」ということにトコトンこだわっています。 「わかりやすい解説を読んで理解する」⇒「問題を解く」の繰り返しで自然に入試に合格するレベルまで身につくように作ってあります。楽典は実技の試験とは違い、きちんと勉強しておけば満点を取ることが可能です。ぜひ「満点」目指してこれから楽典の勉強を始めましょう!
【商品名】音大受験講座!わかりやすい楽典の教科書 川崎絵都夫
【定価】1800円(税別) 【判型・ページ数】A5・168ページ
【発売】全国楽器店・書店
<お問い合わせ先>
株式会社フェアリー 03-5830-7151
E_mail : info@fairysite.com
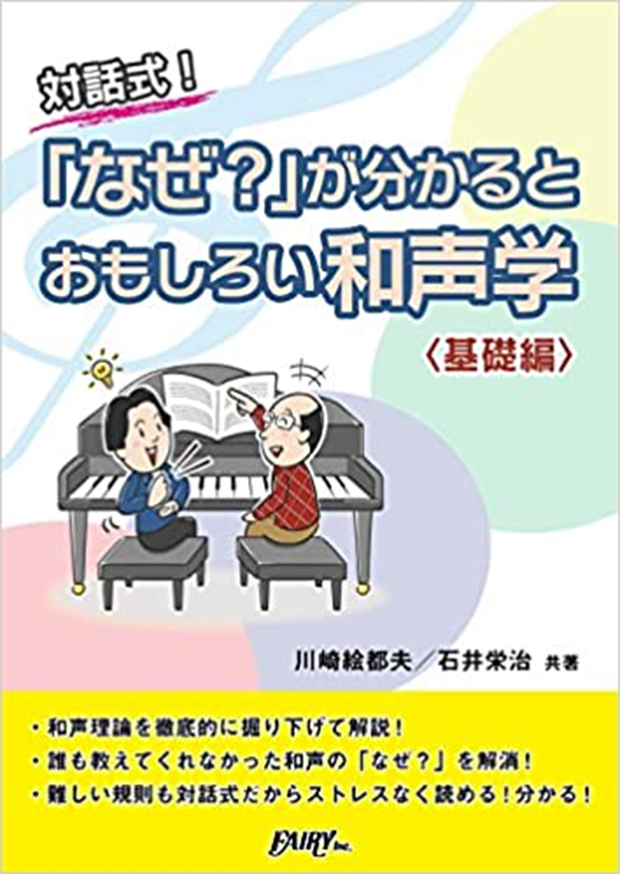
出版社:株式会社フェアリー
「なぜ?」が分かるとおもしろい和声学〈基礎編〉
川崎絵都夫・石井栄治 共著
1,944円
体系的にまとめられた優れた和声学の書籍はすでに数多く出版されています が、この本の特徴は「和声の規則の意味や原理」など、和声学の『なぜ?』の 部分に特にこだわって解説をしています。
さらに、対話形式の文章で実際のレッスンを受けているように分かりやすく、 「和声ってこんなにおもしろいんだ」ということが伝わるよう随所に工夫を こらしています。
「和声学は難しそう」、「和声学に向かい合ったものの、なかなか理解でき ない」という方、音大受験対策など、音楽学習に精を出す全ての人へおすす めの1 冊です。
【目次】
序章 和声学の学習に用いる基礎知識
第1章 和声学の基本
第2章 禁則の基本
第3章 各声部の役割
第4章 機能和声の原理
第5章 和音連結の基本
第6章 第1転回形を含む和音連結
第7章 第2転回形を含む和音連結
第8章 属七の和音
第9章 属七の和音の根音省略形
第10章 反復進行の基本
著書
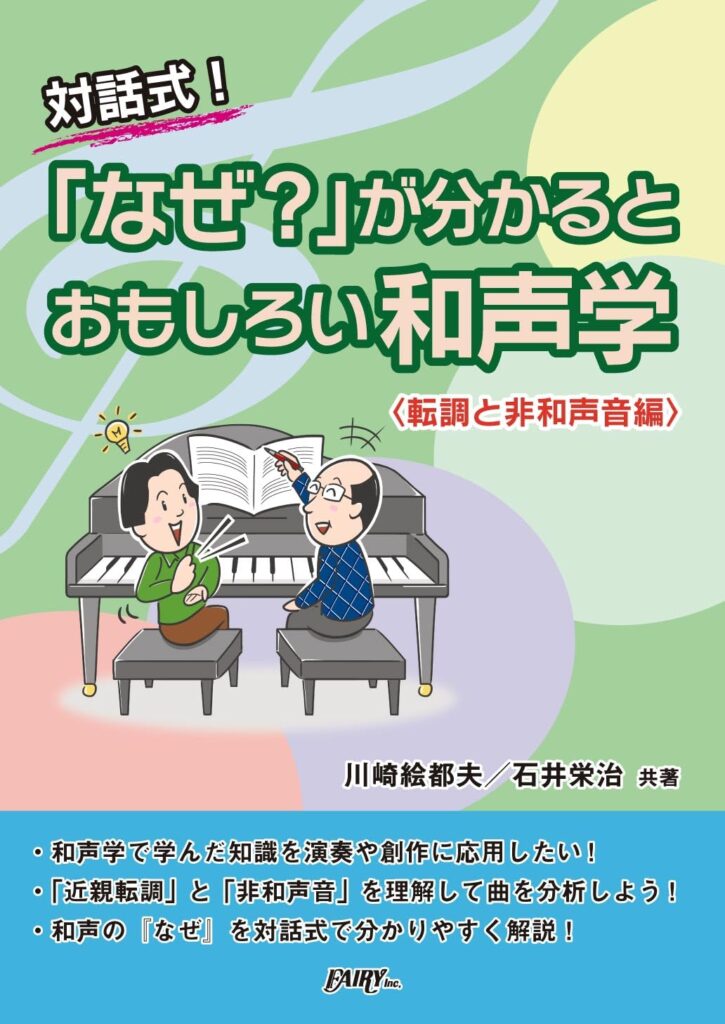
出版社:株式会社フェアリー
対話式! 「なぜ?」が分かるとおもしろい和声学〈転調と非和声音編〉
川崎絵都夫・石井栄治 共著
【目次】
序章 和声の学習~基礎編とその後~
第1章 近親転調
1.『近親調について』
2.『転調に関連する用語』
3.『定調的転調進行』
4.『対斜』
5.『半音階的転調進行』
6.『半音階的転調進行での注意点』
7.『近親転調を含む和声課題の実施方法』
第2章 内部変換と修飾
1.『内部変換と修飾の概要』
2.『内部変換の用語』
3.『三和音の内部変換』
4.『Ⅴ7の和音の内部変換』
5.『形体変換を含むⅤとⅤ7』
6.『内部変換の禁則』
7.『内部変換を含む和声課題』
8.『共通音の結合』
9.『修飾』
10.『修飾音の進行の規則』
11.『修飾を含む課題』
コラム『伴奏音型の革新』
第3章 非和声音
1.『非和声音の概要』
2.『非和声音の種類』
3.『刺繍音の用法』
4.『刺繍音に関する禁則』
5.『倚音の用法』
6.『倚音に関する禁則』
7.『倚音に関する進行の規則の緩和』
8.『掛留音の用法』
9.『掛留音に関する禁則』
10.『逸音と先取音の用法』
11.『経過音の用法』
12.『非和声音によってできる連続及び並達に関する禁則』
13.『孤立4度』
14.『主音上のⅤ』
コラム『非和声音のように聴こえる和声音』
第4章 非和声音を含む和声課題と非和声音の応用
1.『刺繍音を含む和声課題』
2.『倚音を含む和声課題』
3.『掛留音を含む和声課題』
4.『逸音と先取音を含む和声課題』
5.『経過音を含む和声課題』
6.『様々な非和声音を含む和声課題』
7.『掛留音の解決時の修飾』
8.『掛留音が解決されない場合』
9.『複数の非和声音の組み合わせ』
第5章 保続音
1.『保続音の概要』
2.『少数声の和声』
3.『保続低音の用法』
4.『保続低音上の和音連結』
5.『様々な保続音上の和音進行例』
6.『実曲での使用例』
第6章 偶成和音
1.『偶成和音とは』
2.『刺繍和音』
3.『経過和音』
4.『倚和音』
5.『その他』
終章 和声学の楽曲分析への応用